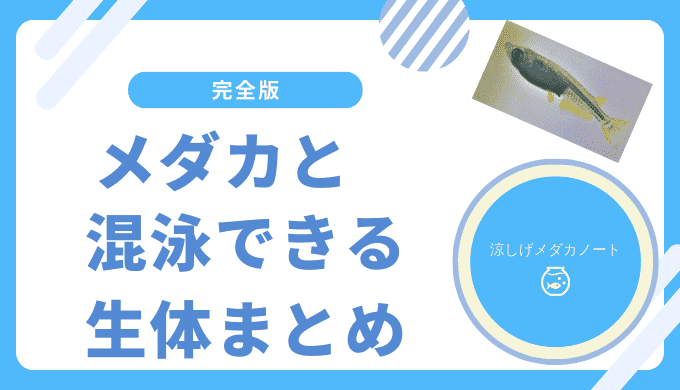著者:長池涼太
この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
メダカに関してはこれまでも記事で書いたけど、今回はメダカと相性のいい生物をまとめてみました。
いろんな生物を飼うとメダカ飼育がより楽しくなります。
メダカと他の生物を混泳させるメリット
メダカのみでも飼育は成り立ちますので、一概にメダカ単独の飼育が良いとか混泳の方が良いとかは言えません。
ただしメダカと相性の良い生き物を混泳させることで、
- メダカのエサの残りを食べてくれる(放置すると水が汚れる)
- 水槽の雰囲気が華やかになる
といったメリットがあります。

大きい金魚飲みたくメダカを食べるなどして相性の悪い生き物はメダカと混泳させない方が良いですけどね。
結局は好みの問題になりますが、メダカ飼育を楽しみたい、ステップアップしたい方はいろんな生き物といっしょに飼うのもオススメです。
メダカと混泳できる生き物
メダカだけたくさん飼ってもいいけど僕は単調だと思い、他の生き物もいっしょに飼ってみることにしました。
種類によっては
- メダカとケンカする
- メダカを食べてしまう
- 逆にメダカが食べてしまう
という生物もいるのでメダカとの相性は気をつけましょう。
以下で挙げている生き物は、攻撃性もなくメダカと問題なく混泳できています。
ミナミヌマエビ

体長2,3㎝の小さいエビだけど、飼育が簡単ですぐに増えます。
ちょこちょこと動き回っているので、見ているだけでもかわいいです。
ただし、と水草についている農薬には弱いのでこの2点には注意を!
水槽内に付着したコケを食べてはくれるけど、効果を実感するにはある程度の数は必要。
メダカとは一番相性が良いです。

メダカといっしょに飼う生き物としては定番ですね。
ヤマトヌマエビ

ミナミヌマエビより一回り大きいエビ。
体が大きい分、ミナミヌマエビより水槽内に発生したコケをたくさん食べてくれる。
数匹程度でもコケを食べた効果は実感できます。
元々淡水の生き物ではないので、繁殖はしない・困難です。

ミナミヌマエビほどではないですが、メダカといっしょに飼う生き物としては定番。
ミナミヌマエビよりコケをたくさん食べてくれます。
石巻貝(イシマキガイ)

見た目は少し地味な貝だけど、水槽内についたコケを取る(食べる)能力に関してはトップクラスと言っていいくらい。
水槽の中が見えないレベルのコケも、1か月くらいでキレイにしてくれました。
繁殖はしないこともないけど一般に飼われている水槽で繁殖した例はほとんどない。

普通に飼うと繁殖はぼぼ不可能ですが、コケを取る能力は今回紹介する生き物ではかなり高い部類です。
フネアマ貝
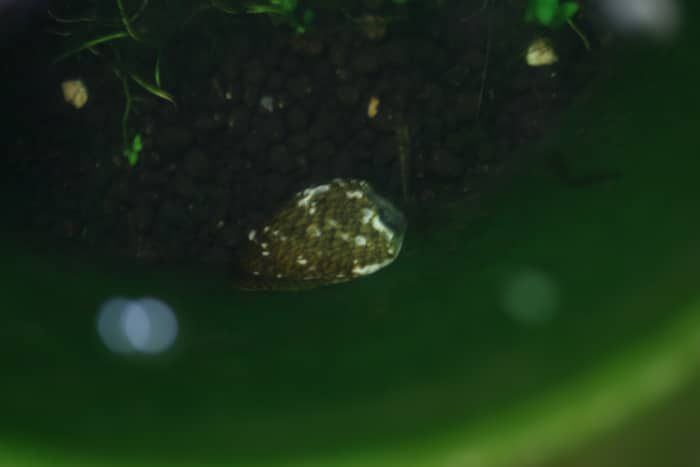
大きさやパッと見の形などは石巻貝にそっくりですが、石巻貝と比べると全体的に平べったい形なのが特徴です。
フネアマ貝の特徴は何と言ってもコケ取りの効果の高さ。
石巻貝やヤマトヌマエビなど水素のコケを取る(食べる)生き物はいろいろと飼ってきましたが、おそらくその中でも最強クラスだと思います。
実際僕の水槽でコケだらけのものがありましたが、だいぶキレイにコケを食べてキレイにしてくれました。
石巻貝と同様で淡水では繁殖はしないので『増やす』ことには期待できません。

コケ取り効果の高さに尽きますね。
ただ実店舗だと石巻貝と比べて扱っているところが少ない印象なので、Amazonなどネット経由の方が入手はしやすいみたいです。
タニシ

石巻貝と同じく貝ではあるけど、タニシはコケを食べるというより水中の有機物(汚れのもと)を食べてくれるので、タニシ自体が水質浄化をしてくれます。
石巻貝と違い、タニシはオスとメスの両方がいれば繁殖はします。
卵は産まず体内で孵化した稚貝が、そのまま出てきます。

水中の有機物を食べてくれるという意味では、動くろ過機といってもいいくらい。
元々メダカと同じく田んぼに生息してるので、メダカとも合います。
シマドジョウ

大きくなっても10㎝に満たないくらいで底の方でじっとしているので、他の生物の邪魔などにもなりません。
地面に落ちてきたメダカのエサの残りなどを食べているので、エサはやらなくても大丈夫。

底にいることが多くおとなしいので、メダカに危害を加えることもありません。
ドジョウによっては攻撃的な性格のドジョウもいるので、メダカといっしょに飼うならシマドジョウが良いですね。
オトシンクルス

写真みたいに壁に張り付くなどして水槽の壁などについているコケを食べてくれる。
こう見えてナマズの仲間だそうです。
コケを取る効果は高いですが、コケを食べつくしてそのままにしておくと餓死することもあるのでちゃんとエサをあげよう。

飼育の難易度は、貝やドジョウなどと比べると少し高いです。

熱帯魚の部類なので、水温を高く保つのは必須。
繁殖は未知数ですが、コケを取るという点においては良い感じです。
ただし、飼ってから死ぬまでが一番早かったので飼育の難易度は少し高いかも…。
スネールは止めた方が良い

まれに入れてもいないのに貝がいる場合があります。
それはサカマキガイなどのいわゆるスネール(害貝)と呼ばれる貝です。
メダカを襲うなど直接の被害はありませんが、異常な増殖や大量のフンで水が汚れるなどのリスクはあります。
(数匹だったのが、いつの間にか数十匹に増えるなんてこともあります)
そのため、スネールは基本的に駆除をオススメします。
メダカと相性のいい生き物はいっぱいいる
メダカだけでの飼育もできますが、ミナミヌマエビなど他の生き物もいることで水槽がだいぶ華やかになります。
メダカなどの観賞魚を飼うこと、いわゆるアクアリウムというのは本当に癒されます。
心身が疲れていて、癒しが欲しい方。
アクアリウムとかやってみると、本当に癒されますよ。
メダカ用品送料無料