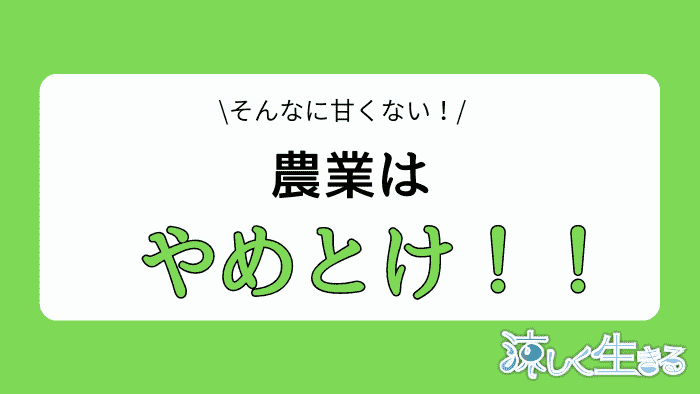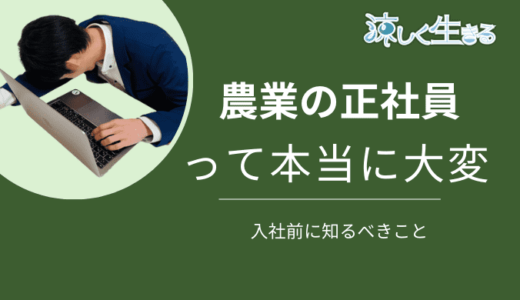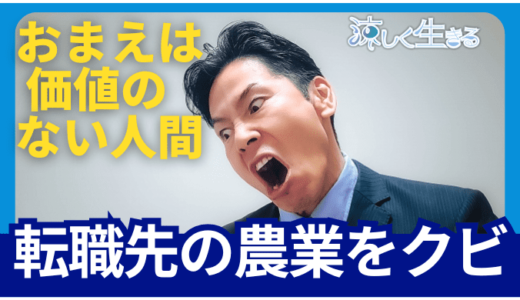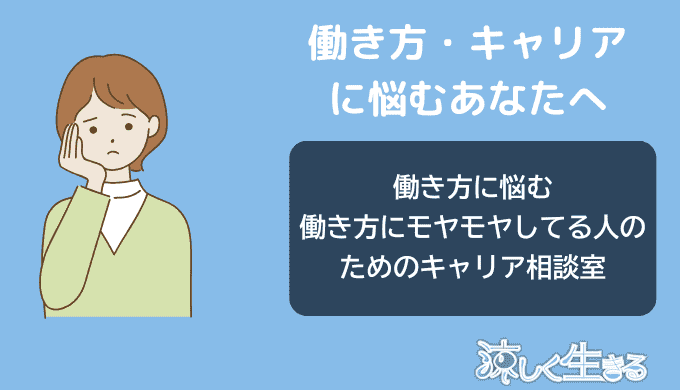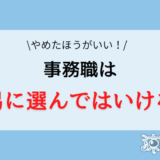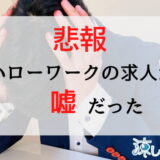著者:長池涼太(ブラック企業研究家)
この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
27歳のとき、僕は4年勤めた学習塾を辞めました。
このとき就職先など何も決めずに辞めたので、そもそもどの業種・職種を目指すかも決まっていませんでした。考えた末、大学の農学部を出ていたことと自然に関わる仕事がしたい思いが再燃したこともあり、農業系の会社を希望しました。
そして1ヶ月くらい転職活動をした末に地元の農業法人に転職しましたが、入社3週間でパワハラに遭った上にクビになりました。今回の記事では、農業方面への就職・転職をお考えの方に向けて農業業界の実態や農業が向いている人・向いてない人などを解説しています。

ブラック企業研究家
長池 涼太
職業紹介責任者の資格所持。大学でのブラック企業に関する授業登壇の実績あり。当メディア涼しく生きる運営。
ブラック企業において過労死寸前の長時間労働やパワハラを経験。その経験をもとに大学などでブラック企業の実態やブラック企業で壊されたキャリアの再生方法等を解説。
僕が転職活動で農業の求人を見て感じたのが全般的に給料が低いこと。
他の業界は正社員で20万円前後が多い印象でしたが農業となると20万円に届く会社がほとんどなく、給料が15万円に満たない会社もたくさん見かけました。

正社員で給料12万円とかありましたが、あくまで税金が引かれる前の額なので手取りで言うと10万円を切る可能性もありますね。
パート・アルバイトについても同じような状況で、最低時給ラインレベルのところが多いです。僕が勤めた農業法人もアルバイトで入ったときは、最低時給+3円の時給(2016年当時)でした。
給料と同じく社会保険や福利厚生が整っていない会社も意外と多いです。
最近では育休・産休なども推進されていますが、特に地方の農業系の会社だとこの辺が整備されてる会社はほとんどないです。社会保険も未加入も会社を意外と見かけますが、厚生労働省では社会保険の加入必須の流れもあるのでいずれは社会保険未加入の会社は減ると思われます。
なお、社会保険の加入条件などについては厚生労働省でも発信されていますので是非ご覧ください。

2022年11月時点で『従業員数101人以上』の会社は条件を満たせば社会保険はパート・アルバイトも必須。
さらに2024年10月には『従業員数51人以上』の会社も同じく必須になるそうです。
最近は機械化もある程度進んできてはいますが、それでも人の手でやる作業が完全に消えるわけでもありません。僕がいた会社では収穫などの作業で出てきた大量の残渣(ざんさ=葉など植物の残骸)を運んだりなど力仕事の比率もかなり多かったです。
あくまで体力仕事そのものが悪ではないですが、農業において体力と筋力は必須だと思いましょう。

ブラックかどうかは関係なく農業がそういう仕事なんです。
農業業界には全体的に休みが少ない傾向があります。これは会社がブラックだというのもありますが、何より植物を相手にする以上は植物に手を付けない時期があまり長いのも問題です。枯れてしまうこともありますからね。
休みが少ないから一概にダメ、ブラック企業とも言い切れませんが植物相手にする以上は植物に合わせたスケジュールにせざるを得ないので、多少休みが少ないのは覚悟しましょう。

年間休日100日を超える会社は少ない印象ですね。
僕は農業法人に転職しましたが、入社3週間でパワハラに遭いクビになりました。
ある日の朝、それまでの慣れない仕事でミスで社長や上司の怒りも積もり積もったものがありましたが、ついに上司をキレさせてしまい、たまたまそばにいた社長の耳にも入ってしまいました。その日の仕事終わりに、30分くらい説教を受けた上に「おまえは価値のない人間だ!」と言われ、そしてクビを宣告されました。

いろいろあって、書面上はクビではなく「退職勧奨」。
退職勧奨の詳細は能力不足で退職勧奨⁉会社を辞めてほしいと言われたらで詳しく解説しました。
あくまで体感ですが、他の業界と比べると体系的に人材育成している農業の会社はかなり少ないと感じます。そのため、新卒はもちろん既卒であっても社内で『育成』することがちゃんとできる仕組みが業界としてあまり整っていないようです。

だから農業業界はいつまでたっても人材不足(若者不足)なのかもしれない。
だから技能実習生などに頼らざるを得ない。
農業の会社の多くは地方、田舎の方にあることが多いです。人口がそれほど多くない地域のため、東京でよくある満員電車とは無縁です。そのため、満員電車など都会ならではの喧騒が煩わしいと思う人にとっては地方、特に農業の仕事をするのもいいかもしれません。
ただし、電車を使わない代わりに通勤用に車が必須になることも多いため、車を持ってないとそもそも就職できないこともあるので気をつけましょう。

僕がいた会社も駅からはかなり遠かったので家から会社まで車通勤でした。
農業系の会社の多くはマイカー通勤などで車が実質必須ですが、「マニュアル免許が必須」な会社が意外と多いです。
半分以上の求人はマニュアル免許必須の記載がありました。
理由は仕事で軽トラを扱うこともあり、しかも軽トラの多くがマニュアル車なためです。
そのため僕のように「オートマ限定」で免許を取ってしまうとマニュアル車が運転できないため、その場合はもう一度教習所に行って「限定解除」という教習を受ける必要があります。
細かいカリキュラムや期間、料金は教習所によりますが、僕の場合は期間は1週間で料金は6万円くらい(2016年時点)でした。

実際に仕事で軽トラを運転しましたが、普段の車とかは見える景色から運転の仕方まで違うのですごく戸惑いました。
幸い車通りの少ない道だったとはいえ、何度かエンストもしました。
農業は植物を扱う以上は自然と関わる仕事の典型です。僕も大学は農学部だったり、昔から動植物は好きだったので元々自然にかかわる仕事はしたいと思っていました。
どこまで関われるかは会社などにもよりますが、自然に関わりたい人にとっては農業はうってつけの仕事です。
これまでも触れましたが、農業の仕事は体力をかなり使います。休みが少ないのもそうですが、重いものを運ぶなど力仕事も多いです。
そのため、「体力がない」「力仕事が苦手」なタイプの人は農業の仕事を苦痛に感じやすいです。
僕がいた会社にもいましたが、将来的に独立して農業をやりたいという方も良いと思います。農業を自分でやろうとすると、作物の育て方はもちろんですが、
- 取引先の開拓
- 農業系の機械の取り扱い
- 人を雇う場合のあれこれ
などもわからないといけません。これらは大学はもちろんですが、社会に出てから独学で学ぶのはかなり難しいため、まずはいったん会社に雇われた上で農業を学ぶというスタンスです。

将来的に飲食店を開きたいという方が、別の飲食店で就職(修行)するという話を聞きますが、これと同じイメージです。
ちなみに僕がいた農業法人も近々独立のために辞めるという方がいました。(社長も公認)
僕は私立大の農学部を出ていますが、大学と農業法人とでやった感じはかなり違うと感じました。大学でも農作業などはやりますが、それ以上に『研究』の要素が強いため実験や研究、論文作成がメインになってきます。
ちなみに大卒で農業系の会社に就職する人は意外と多くありません。食品系の会社など一般企業への就職が大半を占めますし、僕みたく事務や塾講師など農業が全く関係ない仕事に就く人も多いです。

会社の実務の内容で言えば、大学より農業高校の方が近いそうです。
知人が農業高校を出ているので学校でやったことを聞いてみましたが、まさに『農家』って感じの内容でした。
- 野菜を育てる
- トラクターなど農業の機械の捜査
- 野菜の運搬、販売
などいわゆる実習がメインで
大学の農学部でやるような科学的な実験などはあまりやらなかった
とのことでした。このことからも農業法人の実務内容は大学の農学部よりも農業高校の方が近いと思いました。
ちなみに農業高校の卒業後の進路は進学と就職が半々くらいで、特に就職は「実家の農家を継ぐ」「飲料メーカー」「その他飲食絡みの企業」が多いそうです。
農業もそうですが、地方での仕事や自然に関わる仕事となると、
- 忙しい日々から逃れてのんびり過ごせる
- ゆったりと仕事ができる
- スローライフを実現できる
というイメージをお持ちの方も多く昔の僕もこのようなイメージは持っていました。ただ実際に地方で農業をやってみると、いわゆる『ゆったりさ』はほぼ皆無でした。僕は事務や塾講師、運転代行など様々な業界を見てきましたが、他業界と比べても瞬間的な忙しさは上位に入ると思います。
- 給料が低く福利厚生も整ってない会社が多い
- 仕事自体が体力仕事で、休みが少ない
- 体育会系の雰囲気が他業界より強い
- 世間一般が想像しているゆったりした雰囲気は皆無。むしろ忙しい
「自然に関わる仕事がしたい」「ゆったりとしたい」といった理由で農業をやりたがる人もいるそうですが、入ったらギャップで間違いなく打ちのめされると思います。農業業界自体が大なり小なりブラックな体質もありますが、それを差し引いても植物を扱う以上はやむを得ずハードワークになりがちなところもあります。
ぜひ実態を知ったうえで農業の仕事に就いてもらえればと思います。