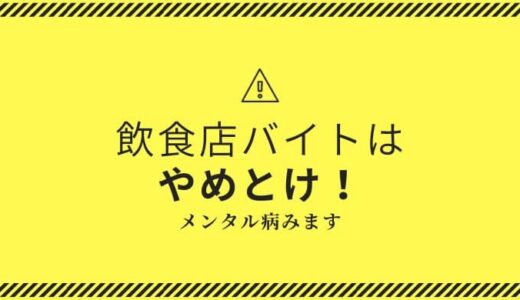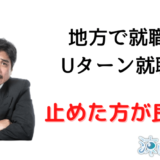著者:長池涼太(ブラック企業研究家)
この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
職場を転々として約5年間会社員をやってきましたが、特に気になっていたこと。
それが「他人が怒られているのが気になってしょうがない」
自分が怒られるのももちろん、自分に関係ないことでも誰かが怒られているのが見えたり耳に入るのも嫌でした。
会議でつるし上げられる上司たち
「誰かが怒られているのを見るのがストレス」、これが特に顕著だったのが僕が塾講師をやっていた頃。塾講師のときに僕は出世しなかったのが幸いしてか、僕が個人的に社長に怒られることはあまりありませんでした。その代わり教室長など責任の大きい立場になると、教室の生徒数の減少や成績不振などで責任を負って怒られることも多々ありました。
それを僕は見ていました。特に印象に残っているのが、2014年の2月某日。

その日は前日が大雪でした。そのため、その日授業のあった生徒の保護者からも
- 「今日って授業あるんですか⁉」
と電話で確認されたくらいでした。そんな大雪のため一部の社員は出勤できず授業ができずに休校にしました。
出勤できなかったことに社長が気にいらなかったそうで、翌日の全体会議では出勤できなかった数名の社員にものすごい剣幕で怒鳴りつけ、その後始末書を書かされた感じでした。塾講師を4年間やっていましたが、社長が一番ブチ切れたのがこのときでした。
誰かが怒られているのを見るのがつらい
ピンとこない人もいるかもしれませんが、自分に関係ないことでも誰かが怒られているのを見たり聞こえたりするのが思いのほかしんどいのです。怒られているに限らないですが、単純に雰囲気を察知しやすいとかもあります。僕で言えば、上司からの見えないプレッシャーも変に感じ取ってしまっていたときは辛かったです。
ちなみに「怒られている人を見るのが辛い」というのは変な話かもしれませんが、テレビを観てても感じます。
- ドッキリで大御所の芸能人などがキレる演技をする
- ドロドロしたドラマ(昼ドラ、サスペンス、ホラーなど)
あたり。特にここ数年、ドラマは全く観なくなりました。テレビの雰囲気も自分事のように感じやすいので、テレビもなるべく観ないようにしています。
怒鳴り声が聞こえた飲食店
昔、某チェーン店で食事をしていて突然店内の放送がオンになったと思ったら、店内中に怒鳴り声が響き渡りました。おそらく厨房かどこかで上司が部下を叱っているような感じでしたが、いきなりだったのですごくビックリしました。
僕もそうでしたし、店内の空気が凍りついたような感じはありました。その後、お詫び?として割引券をもらいました。

飲食店は何かと怖いイメージがある…。
理不尽に怒られた経験
小学生~中学生の頃の話。僕の学校はまあまあ荒れてたので、誰かが怒られているのを見る機会はしょっちゅうでした。僕が何かやらかして怒られることはほとんどありませんでしたが、友達などのとばっちりで僕が怒られたことはたまにありました。
印象に残っているのが、小学校にいたある男の先生はなぜか会うたび僕に怒ってました。元々怒りっぽい先生だったとはいえ、なぜ僕が怒られていたのかはいまだに謎です(笑)

おかげで特に小中学生のときは、かなり神経遣いました…。
こういうのもあって、人の顔色を過度にうかがったり「怒ってないかな?」とビクビクすることが多くなりました。今はここまでビクビクしてはいませんが、それでもふとした自分の発言などで相手を傷つけていないかはかなり気にしてしまいます。
怒られているのを見るのが辛いという人もいる
飲食店などふと立ち寄ってお店に関しては仕方ない部分もありますが、会社で人を怒る際は気を付けたいところです。僕も特に塾講師時代に、上司などがつるし上げられているのを見て僕自身は無関係でも見てて気分がいいものではなかったです。
怒られるのが嫌という人は多いですが、怒られている人を見ることに不快感を覚える人も意外といることが知られてほしいです。
ブラック企業や働き方の
情報を発信中!