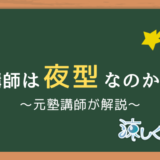著者:長池涼太(HSP研究・エビデンスを発信するブロガー)
この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
2020年以降、HSPがWebメディアやSNSを中心に広く知れ渡り、良くも悪くもHSPを知る人が増えたと感じています。
HSPを発信している僕に「HSPの卒論を書きたい!」という大学生からの相談を受けることもありました。
- HSPを学びたい
- HSPをもっと知りたい
という人も増えている印象で、HSPを学ぶ手段の一つとして「大学でHSPを学ぶ」という人も今後増えると考えられます。
僕もHSPを卒論で扱う大学生の相談に乗ったり、HSPの研究者のセミナーなどに出て最新のHSPの研究情報に触れてきました。その中で調べた「HSPを学ぶために知るべきこと」「HSPを学べる大学」をまとめました。

HSP(Highly Sensitive Person)は1990年代にエレイン・N・アーロン博士が提唱したもので、歴史は20年ちょっと。
日本でHSPの概念が本格的に入ってきて研究されたのは2015年ごろからといわれているため、概念としてはかなり歴史が浅いです。そのため日本国内でHSPを研究したり、HSPを扱っている大学が少ないですし、そもそもHSPの研究者が日本ではまだ数名~10名前後しかいないのが実情です。
大学の授業でHSPが取り上げられることはあるのでしょうか? これもサイト運営者の知る限り、授業でHSPを取り上げる大学の先生は現状でほとんどいないと思っています。
08大学でHSPは学べるか?|Japan Sensitivity Research
大学の卒業研究でHSPをテーマにしたい人は、基本的には、大学の授業で心理学の知識やスキルを身に着けて、それをもとにHSPの論文を読んだりしながら進めていくことになると思います。
HSPを普段の大学の授業で学ぶのは難しいですが、HSPは心理学の一部ですし脳科学や神経、ホルモンなど他の分野も絡んできます。HSPだけでなく心理学全般や脳科学などを学ぶことが、結果的にHSPの理解を深めることにもつながります。

僕も当初はHSPのみで考えていましたが、HSP以外の心理学や遺伝子、神経などの知識も入ったらHSPの研究論文で書いてあることもかなり理解しやすくなりました。
補足
世界的に見れば、日本よりアメリカやヨーロッパなど海外の方がHSPの研究が進んでいたり、研究者も多いです。
直接海外に行くことはないにしても、卒論の参考文献として海外の英語の論文を使うことは避けては通れないので、余裕があれば海外のHSPの情報も集めておくことをオススメします。
なお、海外のHSPの情報については『Sensitivity Research』というサイトにまとまっています。

そもそも日本国内のHSPの論文がそんなに多くないですからね。

僕がHSPの発信をするうえで最も参考にしている方。TwitterでもHSPに関する発信をしていたり、日本で唯一の研究にもとづいたHSPの情報サイト『Japan Sensitivity Research』を運営しています。
元々教育関係の話も多いため、HSPと教育をかけ合わせた話や研究が多い印象です。主に発達心理学や環境感受性の観点からHSPの研究や発信をしています。

2022年11月にHSPの本を出版されました。
研究論文をベースにしているので、卒論にも使えるくらい質が高い本です。
さらに2023年1月には「HSPブーム」に特化・考察した本も出版されています。こちらはHSPの研究知見というよりはメディアやHSP関係者への問題提起の内容が多かったです。

HSPを研究している数少ない研究者の一人で「繊細な心の科学」という本も出版されています。心理学のHSPを研究しながら、文学部の所属ですがHSPに関する研究論文も出されています。飯村さんは主に教育や発達心理学の観点からの視点が多いですが、串崎さんは臨床心理学の観点という違いはあります。
臨床心理学をメインに研究されている方で、臨床心理士と公認心理士の資格も持っています。HSPの研究では小学生向けのHSP(HSC)チェックリストや中学生・高校生を対象にしたHSPチェックリストも研究論文内に掲載されています。平野さんの研究論文を見ていると『レジリエンス』というワードが多いです。
レジリエンスは飯村さんなど他の研究者も言及していることから、HSPにおけるホットワードな立ち位置とも考えられます。
レジリエンスとは、『逆境から素早く立ち直り、成長する能力』と心理学では定義づけられています。
折れない心、しなやかさなどのニュアンスでも用いられます。
良くも悪くも環境に影響されやすいHSPとセットで語られることも多く、HSPとも親和性が高いようです。
岐部智恵子さんは教授や講師といった大学教員とは一線を画す所属みたいなので、学生が直接卒論などを教わるという感じではないかもしれません。ただHSPの研究者を調べると、よく名前が挙がるので挙げさせていただきました。
感覚処理感受性、首尾一貫感覚、ストレス対処を主に研究しており、HSPも主な研究テーマとして挙げられています。研究発表、学会発表にも意欲的なようで、レベルの高いHSP研究に触れることもできそうです。

大学は「心理」「教育」「人文」系統の学部だとHSPは学びやすいみたいです。もしくは飯村さん(創価大学)や串崎さん(関西大学)などのHSPの研究者のいる大学・学部に進学するのも一つの手です。今はまだ、HSPが日本で研究され始めてから日が浅いため、HSPを学校で体系的に学べる場も非常に少ないです。
書籍も売られていますが質がピンキリで特に卒論以上のレベルだと、大半のHSP本はエビデンス(根拠)などの面から卒論の参考文献としては使うに値しません。

むしろ学術的な面のHSPについて書いてる本が非常に少ないです。
現状売れてる本、ベストセラーの部類に入る本はほとんどが質が低いです。まだ少ないですが、
- HSPの研究者が著者の本(アーロン博士でもOK)
- 研究論文を参照にしている本
あたりを選ぶようにしましょう。逆に
- 公認心理士、臨床心理士の資格を持ってないカウンセラーが書いた本
- HSPを診療科目にしている病院や精神科医が書いた本
- スピリチュアルの関係者が書いた本
あたりはHSPの専門家ではないですし、学術的なエビデンスに欠けるなどの点からオススメできません。
では、『卒業論文』でHSPを扱った例はあるのか?
- 心理
- 教育
- 人文
- 福祉
の系統の学部が多い印象です。
大学・学部としてHSPに取り組んでいるというよりは、学生が単体でHSPを扱ったものがほとんどです。
2020年度にHSPを卒業論文で扱った学生がいたそうで、その論文をベースに作った新たな研究論文が掲載されています。
- Highly Sensitive Person (HSP:敏感な人)傾向が日常生活に及ぼすストレスの影響について-ストレスを軽減するためには-
- 日本ではHSPを扱っている大学や大学教員はあまり多くない
- HSP以外の心理学全般やいっしょに扱うことの多い脳科学や神経科学も学ぶと、HSPの理解を深めやすい
- 一部の大学だが、ネット上でHSPの卒論実績は掲載されている
- 主に心理、教育、人文系の学部でHSPを卒論で扱った実績がある
日本ではHSPの研究が始まってまだ数年しかたっておらず、わかっていることも意外と多くありません。HSPを大学で勉強、研究するには今のところは心理や教育、人文系の学部に進学するかこの記事で触れた研究者・教員のいるところに進学するのが現実的かと考えられます。現在ネット上にもHSPの情報はたくさんありますが、大半はあからさまに間違っているなど質が悪くゆがんでHSPが伝わってしまっています。
一人でも多くの方がHSPを正しく学んで、正しいHSPの認識が普及できればと思います。