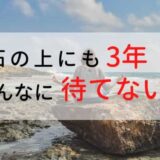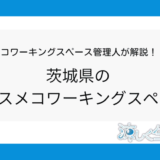著者:長池涼太(HSP研究・エビデンスを発信するブロガー)
この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
今回の記事のテーマは「HSPは仕事が続かないのか?」
僕も派遣事務は2ヶ月と農業は3週間と短期で辞めているので、仕事が続いていません。
同じく短期間で仕事を辞めてしまったり、辞めないまでもやめようかどうか悩んでいる人もそれなりの数がいるような印象です。
そこで今回の記事はHSP気質から見た仕事が続かない理由と仕事をする上で大事な考え方を紹介しています。
HSPはなぜ仕事が続かない?
刺激に疲れてしまうから。五感や雰囲気
HSPの大きな特徴が音や光、匂いなどの五感に関する刺激や会社内の雰囲気(ピリピリしているなど)にも過敏に反応してしまう傾向があります。
騒がしい職場であれば音のストレスが、HSPでない人と比べて蓄積しやすいです。
またピリピリした雰囲気を敏感に察知するタイプの場合も、ピリピリした環境下にいればストレスが溜まりやすいです。
これらによって働きづらくなったり、体調を崩してしまうこともあります。
職場の環境が自分に合うかはかなり重要なことなのです。

職場だろうと家だろうと雰囲気はすごく気になってしまいますね…。
人間関係に悩みやすい(合わない人との関係)
HSPに限った話でもないですが、仕事を続けるかどうかの判断として「人間関係」はかなりウエイトが大きいです。
僕も2か月で辞めた派遣事務は部署内の人間関係は最悪で
誰もお前のことを信用していない!
とまで言われましたし、3週間でクビになった農業法人も誰からも相手にされないし、クビになるときに社長から人格否定の説教を30分も受けました。
一方で4年続いた塾講師は長時間労働が常態化しているなどで労働環境は良くなかったです。
ただし、人間関係は比較的良かったのでそこが仕事を続けられた要因かと思います。
上記で触れた派遣事務や農業と違い、新卒採用を定期的にやっていてそこまで閉鎖的な空気感もなかったのもあり、馴染めることができました。

塾講師時代は休みの日に上司や同僚とフットサルやバスケをやってましたし、僕が辞めるときも送別会まで開催してくれました。
自分の能力を活かせてない
こちらもHSPだけの話でもないですが、自分の能力を発揮できているかどうかも重要です。
例えば塾講師をやっていたときに最初は

「生徒を引っ張り上げよう!」
と思いながらやっていましたが、あまり上手くいきませんでした。
やってみてわかりましたが、かなりの技術が要求されますし、場合によっては生徒がひいてしまうこともありますからね。
そこで3年目あたりからは、
- 生徒に寄り添う
- なるべく生徒と同じ目線に立つ
ということを心がけました。
この効果か生徒の成績も伸びやすくなり、茨城県でいうと水戸一高や日立一高、茨城高専など県内のトップ~それに近いレベルにも生徒を合格させることができました。
もちろん生徒を引っぱる方が向いているタイプもいます。
ただ僕はそうではなかったので、僕ができるやり方で最大限の能力を発揮しました。
HSPは仕事ができないのではない。自分を活かせる場所が大事
HSPが仕事を続けるためのコツ
職場環境は大きなポイント
HSPの観点でも職場環境は重要な要素です。以下のような職場環境だと働きやすいと考えられます。
- 静かで落ち着いた環境:
騒々しい音や刺激が少ない職場環境は、集中力を高まりやすいです。静かなオフィスや個別の作業スペースがあるとより良いです。 - 柔軟なスケジュール:
長時間誰かといたり、忙しい状態では疲れやすいことも多いです。柔軟な勤務時間や休憩時間をしっかり確保できるのもポイントですね。 - サポート体制:
HSPに限らないですが、理解のある上司や同僚、ある程度規模の大きい会社であればカウンセリングやメンタルヘルス支援の提供、サポート体制が整っている職場だとより安心です。
HSPに限った話ではありませんが、『環境』『スケジュール』『サポート』。この3つがしっかりしてる会社であれば働きやすさとしては悪くないですね。
自分ではコントロールできない部分もありますが、自分に合う環境を知るだけでもだいぶ違います。
HSPに合う職場環境を見つける方法
ストレスを軽減する
HSPは外部の刺激によってストレスを感じやすい部分もあります。
細かい方法は人によりますが、以下の方法は割と万人向けでストレスを軽減につながりやすいと思います。
- リラックス法の実践
深呼吸、瞑想、ヨガなどのリラックス法を取り入れることで、心身のリラックスを促すことができます。日常的に少しの時間をリラックスに使うことで、ストレスへの耐性を高めることができます。 - 過密日程を避ける
予定が詰まっていたり、時間的なプレッシャーがあるとストレスを感じやすくなります。余裕をもったスケジュール作成や優先順位の設定をすることで、ストレスを軽減することができます。 - 健康管理
十分な睡眠、バランスの取れた食事など規則正しい生活が基本になってきます。
リラックス法や健康管理は体調面になりますが、やはり体調第一です。
体調が悪くなることで仕事のパフォーマンスも落ちます。
過密日程もやりすぎると、体調などに影響する場合もあります。
過密日程も長い目で見ると良いことはあまりないのでほどほどにしましょう。
会社以外の人と接する時間を持つ
会社で何か悩みができたときに、それを会社の人に相談するのが気が引ける場合もあります。
辞めようか悩んでるみたいなレベルならなおさらですよね。
そういうときに学生時の友人、趣味つながりなんでもいいですが、会社とは関係ない人との接点を持っておくのは重要です。
僕も塾講師時代に辞めようか悩んでたときに、高校時代の先輩に再会して会社でのことをいろいろ話して少し楽になったことがありました。
辞める辞めないまで行かなくてもメンタルの負担を減らすという意味で、会社の外の人と接点を持つのは重要です。

自分を客観視しよう。
仕事が続くことがすべてではない
仕事が上手くいって続けば、もちろんそれに越したことはありません。
「石の上にも三年」という言葉がありますが、塾講師時代に長時間労働でボロボロだった僕はこの言葉を真に受けていて、

最低でも3年はやろう…
と考えてなんとか3年はやりました。
ただこの「石の上にも三年」をうのみにするのは危険です。
最近は労働問題から派生して鬱病なども問題になっていますが、まさに鬱などの精神疾患にかかるリスクがあります。
長くやることで仕事の技術が身についたりなどメリットはもちろんありますが、同時に自分を大事にしてほしいなと思います。
【HSP】仕事を辞めたいときのポイント
仕事が続ける気力が少なくなった場合
相談相手やメンターを呼べる人を一人つくりましょう。
今でこそ本拠地で仕事をしている関係で、悩みがあれば相談できる人がそばにいますが、塾講師で消耗してたころは家と会社の往復だったのでなにかあっても相談できる人がいませんでした。
そのため、一人で抱えこんでどんどんストレスが溜まっていくという悪循環でした。
幸い僕の場合は、辞める一年前になって学生時代にお世話になった先輩や先生に再会する機会があり、そこでいろいろと相談できたおかげで手遅れになる前に辞めることができました。
HSPが続けやすいであろう仕事
ここまでHSPと仕事で話をすると、

じゃあ、HSPって具体的に何の仕事ならやりやすいの?
と思うかもしれません。
一般的にHSPというと、その共感性の高さから「カウンセラー」に適性があると言われています。
もしくはその丁寧さから「事務職」もよくHSPと相性が良いと言われていますね。
ただしこれらについてもあくまで一例で、絶対的な指標ではありません。
例えば、僕は事務職で実際に働いたことがありますが地獄でした。
それはそれは鬱寸前までいきました。
あくまでHSP気質との理論上の相性の話なので、実際にあなたにその仕事が合うかはあなた次第なのです。
HSPと一口に言っても、何に敏感かなどは人によります。
例えば僕は音に敏感(聴覚過敏)ですが、同じHSPでも光の刺激に敏感だけど音は気にならないという方もいます。
そのためHSPで適職と一般的に言われていても、あなたに合うという保証はありません。
あくまでHSPは持っている気質の一つで他にも内向型、外向型など人の気質には様々な要素があります。
HSP以外の観点も含めて適職を選ぶのが重要です。
HSPの観点も含めて自分に合う仕事を考える
- 長く仕事を続けることがすべてではない
- 仕事がキツく感じるようになったら相談相手やメンターがいると楽
- ネット上で言われているHSPに合う仕事はあくまで理論上の話。実際に合うかはHSP以外もふくめたあなたの気質によって変わってくる
心から良いと思える職場であればむしろ長く働けるならその方が良いです。
一方で、僕の過去の勤務先みたいなブラック企業というのは本当に多いです。
そういう場合は長く勤めることで、かえって自分が壊れることにもつながります。
そしてなにより、自分に合う仕事に就くことが重要になってきます。
ただしネット上などで言われている「HSPに合う仕事」と言うのはあくまで理論上の話なので、あなたがHSPだとしてもその仕事が必ず合うとは限りません。
人にはHSP以外にも様々な要素があります。
それらを加味しないとその仕事が合うかはわからないので、「HSPだからこれ」ではなく、自己理解をしっかり深めて仕事が合うか合わないかを判断しましょう。