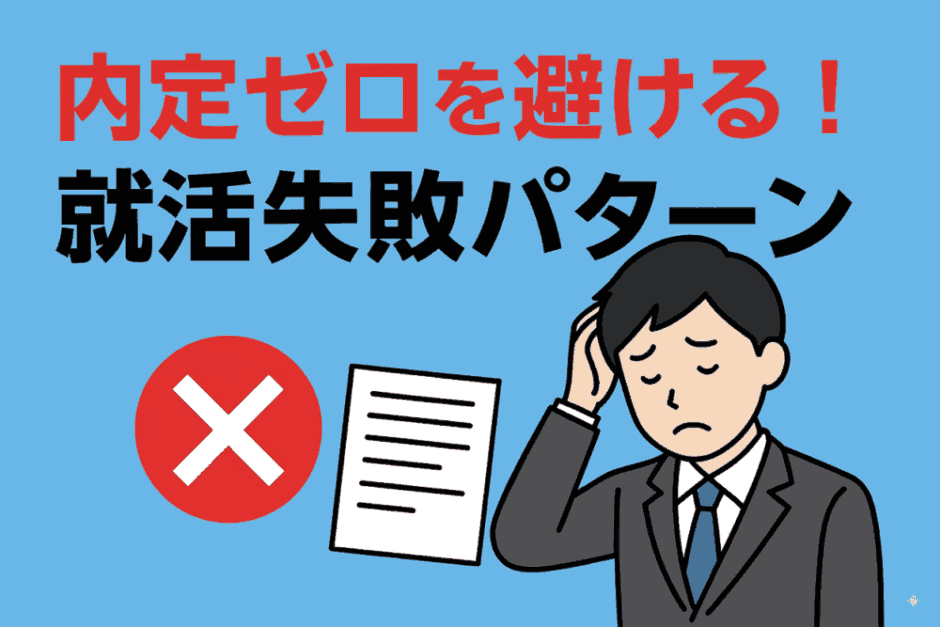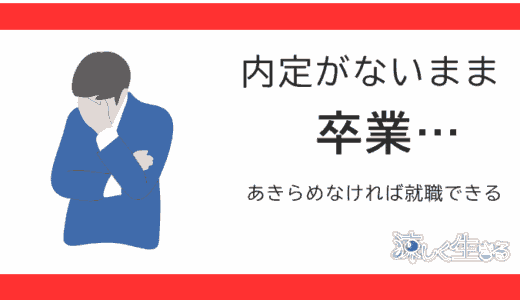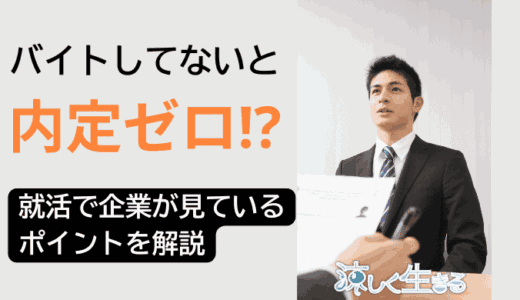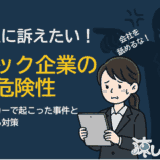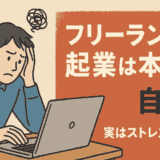著者:長池涼太(ブラック企業研究家)
この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
就職活動の体験談というと「成功談」が多く語られます。ですが、本当に重要なのは「なぜ失敗するのか?」「就活にはどのような失敗パターンがあるのか?」みたいな失敗談ではないでしょうか?
この記事では僕自身の内定ゼロで大学を卒業した就活失敗談をベースに、よくある失敗パターンとその対策を整理しました。これから就活を控える大学生や、就活が思うように進んでいない既卒の方に役立つ内容になっています。

ブラック企業研究家
長池 涼太
職業紹介責任者の資格所持。大学でのブラック企業に関する授業登壇の実績あり。当メディア涼しく生きる運営。
ブラック企業において過労死寸前の長時間労働やパワハラを経験。その経験をもとに大学などでブラック企業の実態やブラック企業で壊されたキャリアの再生方法等を解説。
就活の「成功談」と「失敗談」の違い
- 成功談は条件が人それぞれ(学歴・経歴・時代背景)で再現性が低い
- 失敗談は共通するパターンが多く参考にしやすい
- 「勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし」と同じで、失敗には必ず原因がある
就活に限らないですが、物事において成功した理由は人の数だけ答えがあります。就活に関しても「学歴フィルター」が存在する以上、大学による格差も多少なりとも存在しますし、学部や学科によってもある程度選考を受ける会社も異なってきます。そのため就活を成功させるためのポイントはたくさんの要素が絡むため、考えるのが非常に難しいです。それゆえ就活の成功談を聞いても、学歴などそもそもの前提条件が違う場合も多々あり、意外と参考にならないことも多いです。
「勝ちに不思議の勝ちあり。負けに不思議の負けなし」は、彼が行った藩政改革・剣術や武芸の修行の経験から生まれた言葉なのでしょう。何かに成功するときには、偶然や運に左右される場合が時折ありますが、何かに失敗したときには必ず原因があり、偶然に失敗するということはありません。その原因を解明し、次に同じ失敗をしないようにすることが重要だということが分かります。
松浦 清の名言|Proverb(ことわざ)・格言(名言)|大学受験の予備校・塾 東進
それに対して失敗談はある程度パターン化できます。例えば「面接の受け答えが良くなかった」「履歴書やエントリーシートなど書類の書き方や内容に問題があった」など改善点などはある程度数は絞れます。

ごく稀ですが、選考に落ちた理由を伝えてくれる企業・担当者もいます。
そのためよくある大学等のOB、OGの就活の体験談(成功談)を聞くだけでなく、失敗した場合の視点や対処法も知る必要なのです。
就活失敗談:内定ゼロで卒業
僕が大学生の頃は大学3年の10月に合同説明会等が始まり、そこから就活を進めたものの当時はリーマンショックによる不況や卒業時は東日本大震災も重なったのもあって卒業時点で内定はゼロ。そのまま大学を卒業後も就活を続け、初めて内定を得たのは大学を卒業後の6月でした。
最終的には内定はもらったとはいえ、「新卒」の就活としては失敗でした。
就活に失敗した原因
アルバイト経験がほとんどなかった
- 大学時代のバイトはファミレスを3日で辞めただけ
- 仕送り生活で働く経験がゼロに近かった
- 結果、面接で話せるエピソード(ガクチカ)が不足
個人的に一番大きかったのはアルバイト経験がほとんどなかったことだと思います。大学1年生の5月から某大手のファミレスのキッチンで働きましたが、戦場のような雰囲気の職場で初日から上司に恫喝されるような職場だったため3日行った時点で完全に心が折られてしまいました。
半ばバックレる形でファミレスは辞めましたが、恫喝されていたのがメンタルにも来て当時はその後しばらくホームシックになってしまいました。
アルバイトをやらなかったことによる影響の一つは金銭面。大学生と言えばアルバイトで生活費や遊ぶ金を稼ぐ方も多いですが、当時の僕はバイト代がないぶん、仕送りと高校生の時の貯めた貯金をやりくりしてしのいでいました。
バイトをしなかったことは社会経験の機会損失にもなりましたし、それ以前に普段の生活にも影響しました。
部活・サークル活動にも参加していなかった
- 学生時代に力を入れたことが答えられない
- 自己PRや協調性を示すエピソードが用意できなかった
バイトもそうですが、部活動やサークル活動も一切やりませんでした。部活やサークル活動も面接などにおける「ガクチカ」では定番のネタだっただけに、僕の場合はバイトやサークル等がガクチカのネタに使えない点ではかなりのハンデがありました。
ちなみに僕は中学はソフトテニス部、高校は演劇部と部活はやってましたが、大学入学当初は大学自体に馴染めてなかった部分もありました。そのため部活などに入ろうとも思えなかったですが、こうなると大学に来ても授業受けてすぐ帰るような生活だったので、大学にもそんなに友達はいませんでした。
人とコミュニケーションを取る機会が少なかった
- バイトやサークル等の活動をやらないと人との接点が少なくなる
- 結果、コミュニケーション能力を鍛える機会の損失
大学は1人暮らしでかつアルバイトや部活・サークルをやらないと、人とのコミュニケーションが極端に減ります。僕は元々かなり内気な性格でただでさえ自分からはなかなか話に行けないタイプでしたが、アルバイト等をやってないと、人と話す機会も一般の大学生より少なかったです。
そのためいわゆる「コミュ力」はかなり低い部類だったでしょうし、就活が始まり面接などをしても今考えてもとても上手く・ちゃんと話せた感じではありませんでした。
コミュ力は持って生まれた部分も多少ありますが、結局はいかにたくさんの人と出会い、話したかに尽きると思いました。
社会人として働くイメージがなかった
- バイトや課外活動を避けた結果、仕事のリアルを知らなかった
- 面接で「将来どう働くか」を語れず説得力を欠いた
アルバイトを通じて何かしらの仕事を経験すれば、ある程度でも自分が社会人になってからどんな風に働くかや自分に合うもしくは合わない仕事などもイメージがしやすいです。
僕は就活が始まった段階で「この仕事がしたい」「この業界に興味がある」みたいのがあまりなかったので、とりあえずは地元企業を中心に見て回ってはいました。とはいえ当時の僕の中では「Uターン就職をしたい!」以外はあまり明確に考えてることはなかったので、大学時代の様々な経験値が不足していたから、何もわからない状態だったと思います。
よくある就活失敗パターン
また、バイトや部活・サークルをやっていないこともそうですが、以下のような失敗パターンも僕を含めて見受けられます。
- 学歴フィルターで落ちる → 企業研究と自己分析で差別化が必要
- ガクチカが弱い → アルバイト・ゼミ・インターンなどを活用
- 面接慣れしていない → 模擬面接やキャリアセンターで練習
- エントリーシートの質が低い → 第三者に添削を依頼
学歴フィルターはどうしようもない部分があるにしても、当時の自分を振り返ると面接の練習とエントリーシートの添削はもっと積極的にやるべきだったと思います。
面接やエントリーシートは自分1人での練習は難しく、ちゃんとやろうとすると他人の目が必要です。ただ、大学生の頃の僕は人にダメ出しなどをされるのがすごく嫌な性格だったので、大学のキャリアセンターなどでもできた面接練習やエントリーシートの添削もほとんどやりませんでした。
特に面接に関しては、大学卒業後の就職活動で面接の練習をたくさんしましたが、数をこなすことでどういう受け答えをするかの事前のシミュレーションができたり、何より面接でそこまで緊張しなくなった等の効果はありました。また、面接の練習は面接官の役の日との指摘を受けると、自分が周りからどう見えているかを見つめ直すいい機会にもなりました。
失敗談から得られる教訓
- アルバイトや課外活動は就活に直結する
→ 小さな経験でも「主体的に取り組んだ姿勢」として評価される - ガクチカは事前準備がすべて
→ サークル・ゼミ・ボランティアでも十分アピールになる - 働くイメージを持つことが面接力につながる
→ インターンや社会経験を通じて具体的に語れるようにする
僕がもう一度大学生をやるとしたら、学業を頑張った上で自分に合うものを精査したうえでアルバイトやサークル、ボランティアや地域活動などの学外の活動もやってみたいですね。就職活動って結局は「大学生活を中心に今までの人生でどんな経験をしてきたのか?」を見てると考えられるので、とにかくいろんな経験をしていろんな人と出会うのが、ある意味一番の就活対策だと思います。
僕は今フリーランスですが、仕事の中で地域に出て様々な人に出会ったり、活動に携わったりしていますが、このようなことを本来は大学生の時にやるべきだったかもしれません。

最近は特に地域活動に関わると、大学生に出会うことが多いですね。
就活失敗に関するよくある疑問
- 内定ゼロで卒業したら終わりですか?
- 終わりではありません。既卒・第二新卒向け求人も多く、やり直しは可能です。
- バイト経験がないと本当に不利ですか?
- 不利になりやすいですが、ゼミ・インターン・ボランティアなども立派な経験として語れます。

今は昔と比べて就職・転職サイトも増えましたし、第二新卒へのフォローも手厚くなった印象はあります。
まとめ
就活失敗談から学べることは多いです。自分の経験からわかったのは、
- アルバイトや活動経験不足
- それにより働くイメージを持てなかったこと
が大きな要因でした。これから就活をする人は、僕と同じ失敗を避けるために、在学中から たくさんの人と出会い小さな経験を積み、ガクチカを準備すること をオススメします。
就活でつまずいても大丈夫。失敗から学んで次に活かせば、道は必ず開けます。