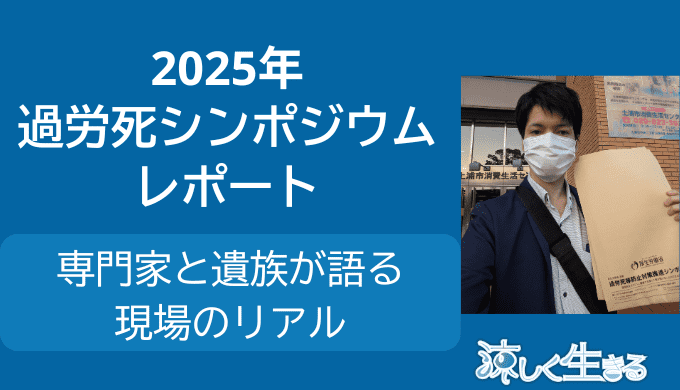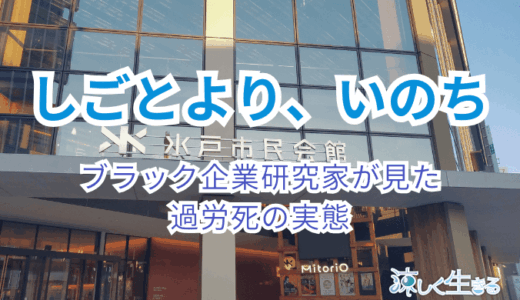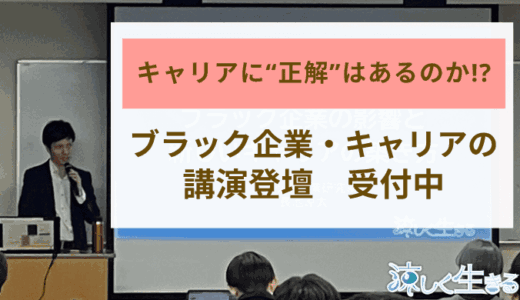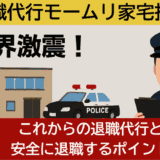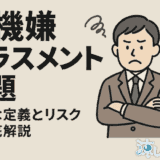著者:長池涼太(ブラック企業研究家)
この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
2025年11月7日に茨城県土浦市の亀城プラザで開催された過労死等防止対策推進シンポジウムに参加してきました。
毎年11月は「過労死等防止啓発月間」と位置付けて過労死のシンポジウムが全都道府県で開催されています。昨年も11月に水戸で開催されて今回が2回目の参加。今年も過労死や労働時間の専門家、企業の事例、過労死ご遺族の話を通じて過労死をより知ることができました。なお昨年参加時の模様は以下の記事で解説しています。

ブラック企業研究家
長池 涼太
職業紹介責任者の資格所持。大学でのブラック企業に関する授業登壇の実績あり。当メディア涼しく生きる運営。
ブラック企業において過労死寸前の長時間労働やパワハラを経験。その経験をもとに大学などでブラック企業の実態やブラック企業で壊されたキャリアの再生方法等を解説。
当日の内容
- [主催者挨拶]茨城労働局
- [基調講演]「パワハラの発生は予防できるのか?過労死のない社会を目指して」津野 香奈美 氏(神奈川県立保健福祉大学大学院 ヘルスイノベーション研究科 教授)
- [企業による事例紹介]「働き方改革は生き方改革 ~カゴメの進化~」カゴメ(株)茨城工場
- [過労死ご遺族による体験談発表]
茨城労働局のホームページでも当日のフォトレポートが公開されています。
茨城労働局
茨城労働局からは統計データを用いた長時間労働の解説。勤務間インターバル制度への言及もありました。また、過労死に関しては女性や医療業界で増加傾向にある点も興味深かったです。

勤務間インターバル制度については以下の記事でも解説しています。
基調講演
神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベーション研究科教授の津野香奈美さんによる基調講演。主にパワハラなどのハラスメントの観点からの講演でした。
初めて聞くワードもいくつか出てきてその一つが『インシビリティ』。
「インシビリティ(Incivility)」とは、礼儀や尊重を欠いた行動や言動を指します。例えば、無視する、話を遮る、皮肉的なコメントをする、感謝を表さないなど、攻撃性は高くないものの不快感を与える言動を指します。職場でのインシビリティは、直接的なハラスメントやいじめと比べ、表面化されず問題提起されづらいため見過ごされがちです。しかし、積み重なることで職場環境や従業員に悪影響を及ぼし、モチベーションや生産性の低下、離職を招きます。
インシビリティとは|ハラスメントグレーゾーンの悪影響 – 『日本の人事部』
ハラスメントにあたる一歩手前の状況で、この段階で対処しハラスメントの発生を未然に防ぐのも大事ですね。
またブラック企業などで長時間ストレスにさらされ続けると、それを回避する行動をしなくなる『学習的無力感』。
ハラスメントを目撃した時の対処法として、加害者に直接注意するのがベストとしつつそれが難しい場合は話題を変えたり、場の雰囲気を変える『スイッチャー』や当事者が帰るときに「さっきのは嫌じゃなかった?」など一声かけることで職場のみんなが敵ではないことを伝える『シェルター(避難所)』の役割なども重要とのこと。
ハラスメントは当事者だけでなく、職場をあげての対策が必要だと感じました。
企業による事例紹介
続いて茨城県小美玉市にあるカゴメ株式会社茨城工場による事例紹介。カゴメといえば野菜ジュースやトマトケチャップなどで有名な大手企業ですね。
僕が独自にとっているブラック企業・労働問題の統計ではカゴメのような製造業における労働問題は他業界と比べても多い印象ではありましたが、その中でカゴメは働き方改革などをしっかりやっている印象でした。
労働時間目標(年1,800時間)と定めていたり、Outlookを用いたスケジュール調整を徹底活用することで、業務の把握やマネジメントを容易化などをすることでの業務の効率化。また有給休暇の取得率も90%越えなど取り組みに対して成果もちゃんと形になっていました。
令和3年(2022年)にはベストプラクティス企業として茨城労働局の訪問も受けており、茨城県の企業の中でも先進的な働き方改革を実施している企業です。
過労死ご遺族による体験談発表
今回の登壇は2013年に過労死したNHK記者の佐戸美和さんのご遺族でした。
2013年7月24日、首都圏放送センター(現:首都圏局)で、東京都政の取材を担当していた都庁記者クラブの佐戸未和記者が自宅で亡くなりました。31歳でした。翌年5月、労働基準監督署から長時間労働による労災(過労死)と認定されています。
佐戸記者は当時、都議会議員選挙と参議院選挙が続き、連日猛暑のなか取材にあたっていました。参院選の投票日の3日後に亡くなりました。
労働基準監督署は、発症前1か月間の時間外労働時間数が、過労死ラインとされる100時間を大きく上回るおよそ160時間と認定しました。深夜に及ぶ業務や十分な休日の確保もできない状況で、「相当の疲労の蓄積、恒常的な睡眠不足の状態であったことが推測される」「業務と発症との関連性は強い」として過労死と認定しました。
2人の職員の労災(過労死)と働き方の抜本的見直し | 経営に関する情報 | NHKについて
ご遺族の方がおっしゃるには、連日25~26時までの勤務でかつ翌朝の9時~10時には出勤という状態で、時間外労働も過労死するころには過労死ラインを大きく超え、180~200時間という途方もない時間だったとのこと。
本来であればこのような状態になる前に会社側がしっかりと労働者の勤務時間を管理したり、労働時間が多すぎる場合は労働者に働きかける必要がありますが、会社側は特にそういう様子もなかったそう。また会社内も縦割りの雰囲気が強く、男尊女卑な雰囲気が見受けられたり、当時はみなし労働時間制が基本だったり記者は実質個人事業主のような扱いを受けていたりなど過労死につながる要素がふんだんにある印象でした。
加えて2013年の佐戸記者だけでなく、2019年にも男性記者が動揺に過労死しており少なくとも佐戸記者の過労死以降において会社側が労働環境の改善などができてなかったとも取れました。
まとめ
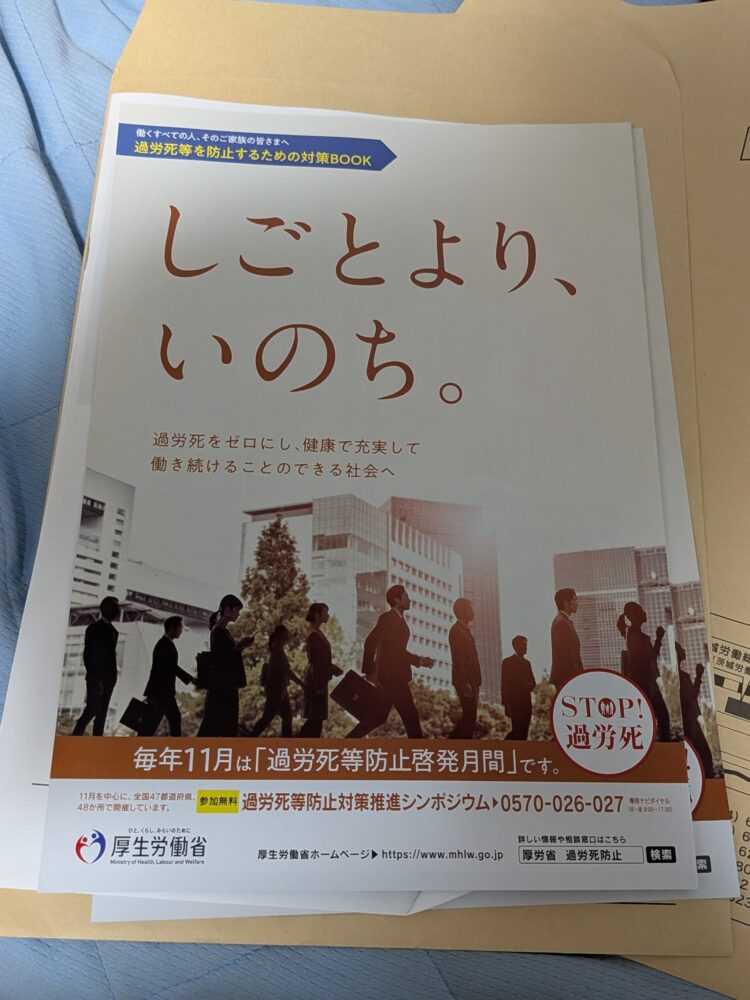
過労死に関しては最近の話でなくずっと前から問題視されていますが、今でも過労死はなくなるどころか減ってはいません。世間一般には過労死のことをもっと知ってほしいと思いますし、企業には過労死を防ぐ様々な対策をしてほしいと思います。
涼しく生きるとしても過労死はもちろん、ブラック企業や労働問題の被害に遭う人が一人でも減るような発信をしていきます。またこのような講演活動や高校、大学等の教育機関での出張授業もやっています。
お気軽にご相談、ご依頼ください。