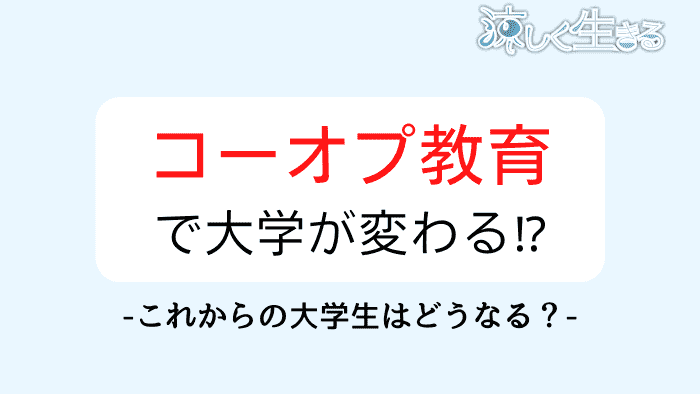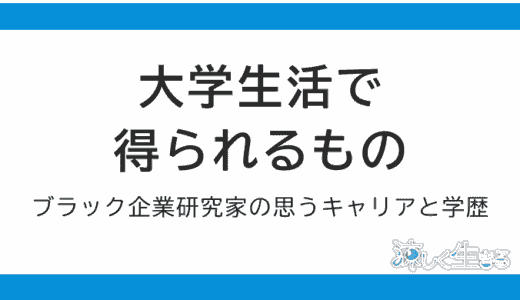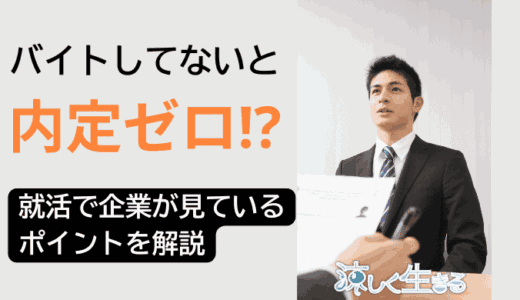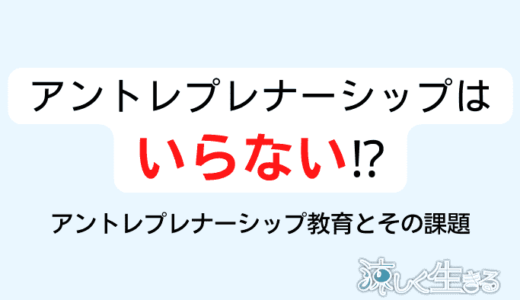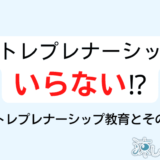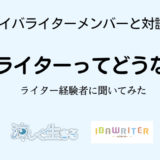著者:長池涼太(ブラック企業研究家)
この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
最近はインターンシップに行く大学生が増えているようです。大学生でいながら企業で実際に働く経験って良いですよね。バイトより実践的なこともできますし。
そんな中、僕の地元茨城にある茨城大学では2024年度より『コーオプ教育』を導入することで話題になりました。最近は一部の学生の間で起業が流行っていますが、コーオプ教育を受けるとどんな変化や良いことがあるのか。
まだ日本ではなじみのないコーオプ教育を数少ない導入例や研究論文をもとに解説しました。

ブラック企業研究家
長池 涼太
職業紹介責任者の資格所持。大学でのブラック企業に関する授業登壇の実績あり。当メディア涼しく生きる運営。
ブラック企業において過労死寸前の長時間労働やパワハラを経験。その経験をもとに大学などでブラック企業の実態やブラック企業で壊されたキャリアの再生方法等を解説。
コーオプ教育とは?
コーオプ教育は企業での就業体験プログラムで大学のカリキュラム内で行われます。インターンシップも企業での就業体験を積む点同じですが、企業が主導する点でコーオプ教育とは異なります。
コーオプ教育(Cooperative Education)とは、就業体験プログラムの一つ。COOP教育とも表記される。
学生の企業における就業体験プログラムとして、日本国内においてはインターンシップが広く知られている。コーオプ教育もインターンシップと同じ就業体験プログラムの一つであるが、インターンシップが企業側主体のプログラムであるのに対し、コーオプ教育は大学側主体のプログラムであるという点が異なる
コーオプ教育 Wikipedia
コーオプ教育とインターンシップの違い
コーオプ教育とインターンシップの違いは下記のとおりです。
| コーオプ教育 | インターンシップ | |
|---|---|---|
| 実習期間 | 3週間~2ヶ月と長期が多い | 1日~14日と短期間が多い |
| 給料 | 原則有給 | 無給が多い |
| 実習前後 | 実習前後に教育プログラムやフォロー有 | 特にない |
| ポイント | 大学と企業が連携して実習を作っている | 企業が主導 |

インターンシップは大学を介さず各自でやるイメージですが、コーオプ教育は大学の授業の一環でやるようですね。大学の授業をしつつ社会経験も積めるとはまさに一石二鳥ですね!
コーオプ教育のメリット
コーオプ教育のメリットは以下の通りです。
- 有給のため経済的な負担が減る
- 実践的なスキルが身につく
- 就職活動に有利
- 大学と企業の連携が進む
- ミスマッチを防げる
研究論文は2012年の阿南高専の論文、2013年の京都産業大学の論文をベースにまとめています。
有給のため経済的な負担が減る
インターンシップは無給でやることが多いですが、コーオプ教育は有給が原則とされています。そのため、大学のカリキュラムをこなしながら働いて給料ももらえることになるので、金銭的にはありがたいシステムです。

特に奨学金を借りてる方はのちの返済を考えても大学生のうちに稼いで、貯金もしておくとより良いです。
もしくは学費も自分で払うとか。
実践的なスキルが身につきやすい
例えば飲食店でアルバイトだと料理を作ったり、ホールなどでの接客がメインになりリーダーやマネージャーなどより実践的な仕事に触れることは少なく、できる仕事に限りがあります。
その点コーオプ教育では通常のアルバイトよりもより専門的・実践的な仕事をすることも多くなります。例えば工学部の学生ならアプリの開発、ものの加工作業など大学で習った専門知識が活かされるものですね。
大学の座学で専門レベルの理論を学び、コーオプ教育(企業)で実践を通じて将来にも使える実践的なスキルが身につきやすいのも大きなメリットです。

ちなみに僕は農学部出身ですがバイトでも卒業の仕事でも農業にはほとんどかかわってないため、コーオプ教育という場で大学で学んだことを活かせるのは良いですね。
就職活動に有利⁉
コーオプ教育での経験は就職活動で履歴書に書いたり面接でも自己PRなどにも使えるようです。アルバイトもそうですが、コーオプ教育はより実践的な実務に関わることも多いため企業からも印象がよさそうです。
新卒というと持っているスキルより『伸びしろ』(若さ)に期待する企業が多いですが、今後コーオプ教育が浸透すると若さに加えてすでに実務経験があるということで、ある程度の経験やスキルがある状態での就活が当たり前になるかもしれません。

就活においてバイトの経験はかなり重要だと感じました。
大学と企業の連携が深まる
これについては学生というより大学側のメリット。コーオプ教育は大学のカリキュラムの一環としてやるため、実施するには大学と企業が密に連携する必要があります。コーオプ教育が上手く回ることで大学は地域社会の貢献になりますし、企業からすると優秀な人材の育成・獲得にもつながります。
会社もそうですが、特に大学などの教育機関は総じてクローズドな場になりやすいため、このように地域との接点を作ることで大学の評判をよくすることにもつながるかもしれません。
学生・企業間のミスマッチを防ぐ
以前から「新入社員がすぐ辞めてしまう」などの問題がありますが、理由は大まかにミスマッチに関することが多いです。具体的には「仕事のストレスが大きい」「仕事が面白くない」「職場の人間関係がうまくいかない」などですね。
コーオプ教育で実際に会社で働き実践的な実務を重ねることで、会社で働くイメージや業務内容のイメージもしやすくなります。何よりインターンシップと比べてコーオプ教育は大学のカリキュラムの一環でやる以上はある程度深く関係を持つことになるので、より企業分析や自己理解が進みミスマッチを減らせると言えます。
コーオプ教育のデメリット・課題
コーオプ教育のデメリットは以下の通りです。
- 長期休みが減ってしまう
- 卒業研究、研究室の配属が自由に決められない
- 就業先の企業の選定が不透明
- 専攻内容と業務内容がリンクしない場合がある
- 導入例が少ない
デメリットは各大学のHPや実例などに情報がなかったので、研究論文で触れられていた課題をピックアップしています。2012年阿南高専の論文、2013年の京都産業大学の論文参照。論文ベースのため必ずしもすべてのコーオプ教育に当てはまるわけではありません。
長期休みの短縮
現状コーオプ教育は夏休みなどの長期休みの期間中に実施されることもあるようです。そうなると単純にそれだけ休みが減ることにもなります。どう取られるかは人によるかもしれませんが、休みが減ることで
- 自動車教習所に通って免許を取る、合宿に行く
- 国内、海外旅行に行く
- 部活やサークル活動
といった定番の活動が難しくなる可能性はあります。

休みの日は休みたいし遊びたりいろんな経験を積みたい人が多いかも。
卒業研究・研究室の配属を自由に決められない!?
基本的に大学の卒業研究のテーマや研究室(ゼミ)の配属は久寿などと相談したうえで自分で決めます。ただしコーオプ教育での就業先によっては、企業の技術課題に合わせて卒業研究や研究室の配属が決まってしまうことがあります。
コーオプ教育によって、自分の配属の自由が利かない可能性があるかもしれません。
就業先の企業の選定が不透明
例えば普通に就職活動をすると自分で会社を選んで選考を受けます。一方でコーオプ教育はどの企業で実務を行うかの選定はいろいろ調べてもよくわかりませんでした。
また、阿南高専の研究論文においても「企業選択過程に企業訪問・工場見学を含める」という要望が学生からあがったらしく、やはり企業の選定はまだ基準などがわからない部分があるみたいです。

コーオプ教育にかかわる企業、学生が実習に行く企業は大学側で決めてしまう形と思われます。
さらに「就業開始前の就業内容の詳しいお知らせ」も要望があったらしく、学生からするといきなり始まった感じも出てしまいそうですね。
授業・専攻内容とリンクした就業内容
大学で学んだ知識を応用できるような就業内容についても学生から要望があったようです。例えば大学で農学部に所属しているなら、農業や食品に関わる企業・就業内容になるとかですね。
ちなみに僕は普通に就職した身ですが、農学部を出ていながら事務や塾講師など農業とは全く関係ない仕事をすることが多かったので、コーオプ教育に限らず大学の選考内容と就職後の実務内容もリンクすればと思います。

農学部を卒業して農業をやる人は意外と少ない。
導入例が少ない
この記事の公開時点(2023年3月)でも大学でのコーオプ教育の導入・実践例はかなり少ないです。後述の茨城大学でのコーオプ教育の導入も日本の国立大学では初めてで、日本の大学でコーオプ教育を導入している大学は数えるくらいしかありません。。
そのため「コーオプを受けられる大学に行きたい!」と思っても、行ける大学や学部が限られてしまいます。とはいえ、徐々に導入例や実例が増えていけばコーオプ教育を導入する大学も増えると思われるので、この辺は気長に待つしかないですね。

先日当ブログで書いたアントレプレナーシップもそうですが、最近は大学でも様々な新しい取り組みが出てきています。
大学でのコーオプ教育の実例
まだ全国的にも導入例は少ないです。ただ一部の大学で導入はされており、
- 東京工科大学
- 京都産業大学
- 金沢工業大学
- 立命館大学
では2022年度時点で導入されています。
東京工科大学。実習前後のフォローもばっちり
文部科学省の平成27年度大学教育再生戦略推進費 「大学教育再生加速プログラム(AP)」に採択されるなど日本でも先駆けてコーオプ教育を導入した大学の一つです。
流れは「事前学修」「実習」「事後学修」の3段階になっていて、学生・企業・大学の3者いずれにもメリットがあるように組まれています。現状は夏休みの期間中に4週間の実習をしています。
京都産業大学。座学と実習を交互に
京都産業大学では企業と連携し、学内の学びと学外の学びをサンドイッチのように積み重ねていく独自のコーオプ教育プログラムを展開しています。学生は企業の現場で求められる能力を知り、学問の重要性を再確認し、広く深く独自のキャリア観をはぐくんでいきます。
コーオプ教育紹介パンフレット|京都産業大学
東京工科大学とは少し違った形式のコーオプ教育を実施しており、『サンドイッチ型』と呼んでいます。大学での座学と実習としてインターンシップとPBL(課題解決型学習)を交互に繰り返す形式で、東京工科大学の座学と実習を明確に分けているパターンとは違いますね。
京都産業大学の場合はそれぞれを短期間で反復するイメージです。
金沢工業大学。企業での実習はたっぷり
KITコーオプ教育プログラム|金沢工業大学
- 4か月以上の長期間のプログラム
- 業務内容について事前に大学と企業で打ち合わせを行い、学生の専門力を把握したうえで業務内容を決定
- 企業担当者を実務家教員として招聘
- 教育評価の上でも指導教員と連携した教育主導による教育評価を実施。事前学習の実施において企業との連携によりコーオプ教育プログラムの教育効果をさらに高める取り組みを実施
- 学生の積極的なコーオプ教育プログラム参加を促すためのキャリア教育を通じた意識の醸成を行う
東京工科大学に近いイメージで座学と実習を明確に分けており、企業での実習は4ヶ月から1年にわたるようです。また、学生が参加したい企業を選ぶことができるのも良いですね。
立命館大学。2005年より先駆けてコーオプ教育を導入
2005年度からコーオプ教育を導入しており、日本ではかなり先駆けてコーオプ教育を実施しています。『理論』と『実践』の2つに分かれており、実践では企業から提示されたテーマに沿って企画立案と提案を行い、理論では実践の基礎になることを講義科目で学びます。
茨城大学も2024年よりコーオプ教育導入
地域未来共創学環でコーオプ教育を実施
この新たな教育組織における教育方法の特徴のひとつが、「学働融合」を志向したコーオプ教育の導入です。地域の企業や自治体などで実際に働きながら学ぶ、ということを、必修の正規課程として組み込み、その一部は有給とすることも構想しています。このようなコーオプ教育を日本の大学で導入している事例は少なく、正規の課程として1年次から全員必修として組み込んでいるのは、国立大学ではまだ例がありません。
<学長会見>分野横断的な学びの場をつくる取組みの構想を発表
40人規模の新教育課程設置、全学副教育プログラム創設
僕が住んでいる水戸市の茨城大学も2024年度よりコーオプ教育を導入することが決まっています。ここまで紹介した東京工科大学などはすべて私立の大学ですが、茨城大学は1年時より必修としては国立大学で初のコーオプ教育の実施になります。
コーオプ教育|地域未来共創学環
- 1年次から4年次の各年次で演習や実習を用意
- 大学で学んだ知識・能力を企業や自治体などで実際に働きながら実践・応用
- 実習で自身に足りない知識や能力を知り大学で学修する「on-Campusとoff-Campusの往還型学修」により高度な実践力を育成!
- 3年次と4年次の実習は給与も支給されます
- コーオプ教育を専属的にサポートする専門職員も配置
- 茨城県内の50を超える多様な実習先!
「地域未来共創学」という工学部、人文社会科学部、農学部をを合わせた学部のような枠組で募集、コーオプ教育を実施予定です。また
- ビジネス(経営・経済)
- データサイエンス
- ソーシャル・アントレプレナーシップ
を身に着けることを重要視しています。
実習予定先の企業はすでに公開されている
ちなみに実習先が予定されている企業はすでに公開されており、
- 旭物産
- 香陵住販
- カスミ
- 常陽銀行
- 茨城いすゞ自動車株式会社
など茨城県内では知名度が高く、優良企業としても名が知られている企業が多いため安心感もありそうです。加えて
- 水戸市
- 日立市
- ひたちなか市
- 那珂市
など水戸近辺の自治体も実習先として予定されています。
茨城大学のコーオプ教育導入を聞いて僕が懸念してたのが「実習先の企業にブラック企業が紛れていないか?」
「ひねくれたこと考えるな!」と怒られそうですが、ブラック企業の発信をし自身も経験してきた身としてどうしても心配になりました。
茨城県のブラック企業の傾向をまとめた記事にて知人などから県内のブラック企業の情報を30社以上いただいていましたが、幸い僕が情報をいただいたブラック企業はコーオプ教育の実習先にはありませんでした。
いい評判を聞くことが多い企業ばかりな印象なので、企業の良しあしに関しては概ね安心していいと思います。
未知数な部分もあるコーオプ教育。ミスマッチ防止には役立ちそう
- コーオプ教育は大学主体で学生に企業での実務経験をさせ、大学で学んだことを活かしたり、自身の就職へとつなげるプログラム
- 日本ではインターンシップが主体でコーオプ教育を導入している大学は少ない
- 大学によってコーオプ教育のやり方は少し違ってくる
- 現状は工学系の大学、学部での実施がほとんど
- 2024年より茨城大学が国立大学としては初のコーオプ教育の導入
メリット
- 有給のため経済的な負担が減る
- 実践的なスキルが身につく
- 就職活動に有利
- 大学と企業の連携が進む
- ミスマッチを防げる
デメリット
- 長期休みが削られる場合もある
- 卒業研究、研究室の配属が自由に決められない
- 就業先の企業の選定が不透明
- 専攻内容と業務内容がリンクしない場合がある
- 導入例が少ない
コーオプ教育は日本では導入例が少ないということでまだまだ課題や未知数な部分も多いです。ただしアルバイトより実践的なスキルが身につきやすかったり、就職後のミスマッチを減らせる可能性がある点は明確にメリットともいえます。
大学にいるうちにしっかりと経験を積んだうえで就職すればミスマッチも減るなど良い影響もあるでしょう。
未知数な部分も多いですが、良い方向に進むことを期待しています。